
-
お電話でのお問い合わせ+595 985-973085
- メールフォーム

パラグアイの大豆について知ろう!

パラグアイの大豆について見ていこう。
パラグアイ、特にイグアス移住地は大豆の不耕起栽培を成功させた地として有名だが、不耕起栽培が始まった当時の事はあまり語られない。
今回は不耕起栽培と当時の世界情勢、知られざるイグアス移住地の苦難なども一緒に見ていこう。
パラグアイの大豆、概要
現在、パラグアイに興味を持ってインターネットで検索をすると日系人の作った功績として「大豆」「ごま」は必ず出てくる情報の一つだろう。しかし、パラグアイへ移民した日本人達は大豆を作りに来たわけではない。
元々、大豆は日常的に自分たちが食べる味噌やしょうゆを作り、自給自足の生活を送る分だけ栽培された。その他に経済栽培(売ってお金に換える作物)用にトウモロコシ、マテ茶、綿などが入植当初は栽培されていた。
大豆の不耕起栽培に転機が訪れたのは1982.1983年イグアス移住地で起こった集中豪雨だ。これにより多くの農家で土壌が流れ出し、大豆の作付が出来なかった。
農家にとって土壌が流れてしまうことはいままで育てた栄養豊富な土を失い、その年の作物がよく育たないということだけを意味するのではない。もっと重大な問題なのだ。毎年のように土壌が流出してしまえば、その土地が持つ本来の土力を失ってしまう。失ってしまえばその土地では作物が育たなくなってしまうのだ。
また、流れ出した栄養豊富な土が川まで流れ込んでしまった場合、川は栄養過多となり植物や魚などの生態系に影響を与えてしまうことも考えられる。その土地の生態系が崩れてしまえば土地を捨てて移動するしかなくなる。
そういった危惧からイグアス移住地の日系農業者がパラグアイ農業総合試験場(CETAPAR: Centro Tecnológico Agropecuario en Paraguay)が普及に努めていた不耕起栽培に着目し、これを成功させ、イグアス移住地を中心にパラグアイ全体へ普及していくこととなったのだ。
不耕起栽培(ふこうきさいばい)
不耕起栽培はパラグアイに定着した画期的な栽培技術だ。アメリカ発祥のこの技術はブラジルに伝播し、1980年ごろ、パラグアイへ伝わり当地にて花開いた。
この栽培方法はその前まで当然とされていた播種(はしゅ)(種まきの意味)をする前に行う畑を耕す作業(耕起)や整地作業を省略し、収穫を済ませた畑に直接播種を行う栽培方法だ。
この不耕起栽培導入の目的は,前述のとおり土壌侵食の防止だ。パラグアイの大豆栽培地帯は緩い起伏のある波状の丘が連なる地形のため、土壌が起伏の高い所から低い所へ流れてしまっていたのだ。その影響でパラナ河は赤い大河と化していた。
その現状を打破する為にこの技術が用いられた。不耕起栽培の一番のメリットは土壌保全と耕起しない事による作業時間の短縮が挙げられる。その他にも適期に播種作業が終わるようになったのも大きなメリットだ。
不耕起栽培が導入される前までは、天候によっては作業が進まない時も多くあった、つまり全体で100の仕事があったとして広大な土地を耕し、整地し、除草し、播種をする作業が必要な場合、一日作業が遅れると一日播種をするのが遅れる事を意味した。
しかしこれが30の作業で済むようになったことで導入以前よりは天候に左右されずに仕事が出来るようになったし、一番良い時期に播種が出来るようになったということだ。
当初、不耕起栽培にもデメリットはあるといわれていた。耕起しないことにより、土壌が撹拌(かくはん)されないことや、肥料、有機物が土壌表面に集積することによって、その肥料を求めて根が浅くなり、干ばつによる影響をモロに受けてしまうのではないかと懸念されていた。
しかし、実際は異なっていた。残渣(ざんさ)(前に収穫した作物の残物)が土地に十分に残っていたことで乾燥を防ぎ、5~6年でむしろ土はやわらかくなった。
また残渣が土を覆うことで、太陽光、雨、風が直接当たらなくなり、地温の上昇が防がれたことは微生物にとって格好の住処となった。これによって、自然の力による回復力で肥沃な土壌が保たれる事に繋がったといわれている。
不耕起栽培導入の背景(イグアス移住地の窮地)
現在、インターネット上でみるイグアス移住地やパラグアイの情報ではあたかも、不耕起栽培がいきなり成功したかのような見出しや、成功の事実だけが書かれているサイトが非常に多く見受けられる。
しかし、不耕起栽培導入以前のイグアスが死に瀕していたことはあまり語られていない。ここでは知られざる過去を見ていこう。
1980年代当時、イグアス移住地はトマトやメロンなどの蔬菜栽培(そさい)(野菜の意味、野菜は市場での呼び方を指す。農業用語では野菜栽培は蔬菜栽培という)の栽培が中心となっていた。1970年ごろから日系社会で普及したトマト栽培は「作れば売れる」といわれイグアスでもどんどんと農地を拡大していった。
しかし移住地内で農地が増えるに従って、トマトや他の野菜は供給過剰になっていった。それに気づいた農家たちはお互いに収穫時期をずらすなどの涙ぐましい努力をしていたが、1970年代に手作業から機械化農業へと移行し始めていた事も重なり、大部分の農家は1980年を境に国際商品として市場が安定している大豆への営農転換を行った。
時を同じくして、1979年にジョポイラ農協(現、イグアス農協)はブラジル銀行から借り入れを行い6.700トンのサイロ建設を決定した。サイロとは収穫した作物を一旦保存する為の設備だ。これによって市場の動向を見ながら最大の収益が上がるように販売する事が可能となる。
その当時、ジョポイラ農協の生産量は2.000~3.000トンでまだまだ大型のサイロが必要とは思えなかった。しかしサイロ建設は組合員の機械化農業推進に大きな意味を持つとしてこれを敢行した。
サイロ建設を後押ししたのは1973~1979年のおよそ7年間、パラグアイの好景気も後押しして、販売と購買事業が順調に拡大して毎年黒字を計上していた農協の収益状況も影響しているだろう。当時は機械化農業へと移行していた時期でもあるから、少なくとも一定数の組員は機械化農業が成功し、今後は更なる農地の拡大と移住地の発展を、、と誰もが考えていても不思議ではない。そして、このサイロ建設を皮切りにジョポイラ農協の経営は難航し、負債の膨張と借金の連鎖による不遇の時代を進んで行く事になる。
この頃を表すキーワードは「サイロ建設の借入金」「機械化」「増産計画の見込み違い」の三点だ。前述の通り、このサイロはジョポイラ農協の生産量を超えた規模と収納能力を備えていた。そして、その返済計画は機械化による増産と作付面積(実際に作物を植える面積)の増加に伴う生産物の増産を見越して計画されたかなり厳しいものであった。
つまり、この三つのキーワードが全て上手くいって初めて返済できる計画だったのだ。しかし大いに期待されたこのイグアス移住地を取り巻く歯車は上手くかみ合わなかった。サイロ建設の借入金は前年比1.4倍の増産をしていかないと利息の支払いに留まり、元本の返済は出来なかった。
そんな中、機械の老朽化に伴う故障や1970年後半には悪天候の連続で1979年に1.229時間の稼働時間だったブルドーザーが1980年には62時間しか稼動する事が出来ず作付面積の拡大どころではなかった。
また、1980年少ない収穫であった大豆を最大の収益で売れるようにと国際相場が上がりきるまで期待していたが上がらず、累計6.432万Gsの損失となった。
さらに1982年にはアルゼンチンの経済が悪化し、それまで行っていたアルゼンチンへの蔬菜の輸出が不可能となり、行き場所を失った蔬菜はパラグアイに留まり供給過剰による値崩れが発生した。
それとは逆にトウモロコシなどの豚や鶏にやる飼料の高騰が養鶏・養豚農家を襲った。これによって1983年を最後にイグアスの養豚農家は廃業に追い込まれてしまう。
すでに目を覆いたくなる状況だが悪いことはまだあった。1982年8月には突風と雹によって、80%の小麦が倒伏した。そして前述してあるが1982.3年、パラグアイでも記録的な長雨により、大豆が腐ってしまった。
それに加え翌1984年には霜の被害を受けた。その時もパラグアイでは記録的といわれる冷夏となりジョポイラ農協の小麦作付面積の90%が被害をうけた。
更に悲惨な状況は続いていく、当時サイロの借入金も機械化に伴う団体融資も個人融資も全てドル建てで行われていたのだが、南米全域におよぶインフラの影響を受けてパラグアイの通貨も価値の減少がおこった。
サイロ建設資金を借り入れた1979年当時、1ドル126Gsであった相場が1982年には1ドル160Gsになり、1984年には240Gsになってしまった。そこから生じる為替差損は農協にとっても個人にとっても多大な被害となったことだろう。
人災、災害に加え、蔬菜の国際相場にも見放され、周りの国の経済悪化に巻き込まれ、更にその影響でインフレが起こり、自国通貨の値下げが起こるという恐ろしい状況が生み出されたのだ。
この状況を表すのは瀕死という言葉以外ないだろう。こういった危機を脱するきっかけを作った不耕起栽培はまさにイグアスの「救世主」と呼ばれてしかるべき技術であった。
当時移民した、日本人の一人はこのように話している「不耕起栽培は瀕死のイグアスを助けただけでなくパラグアイ全体の移住地をも救う救世主だった」と。
脱却・飛翔
苦しい時代は長かった、文字にしてしまえば簡単に感じるかもしれないが1年365日、十分長い月日だがそれの5倍、5年間1825日、ジョポイラ農協はあまりにも長い年月辛酸を嘗めた。
しかし、不遇の時代にじっとたえて、今日の栄華の礎となる年が訪れた。それが1986年と1988年の決算だ。実に6年振りに1986年の決算は事業収益が黒字に転じ、1988年には累積欠損金も解消した。
もちろん、この2年間、天候に恵まれ、、などと簡単な理由ではない。大いなる飛翔には大いなる意味を孕んでいるのだ。
大豆は規模の経済を生かさなくては収益がでない。特に開墾期には設備投資なくして成功はない、例えば1という大きさのトラクターよりも10という大きさのトラクターで作付けを行えば労働時間は10分の1で済むので更に多くの土地に作付を行う事が出来るし、10の量の除草剤を買うよりも100の量の除草剤を買えば購入価格は下がる事になる。
事はそんなに簡単ではないが簡単にいうとこれが規模の経済だ。その為、この時期はJICAや銀行、パラグアイ政府からも支援を受けて機械化を一気に推し進めた。
その結果1986年にはコンバイン20台弱、トラクター40台強、播種機25台、消毒機13台を所有していた。こうして農地の拡張と大豆や小麦を中心とする機械化農業は飛躍的に進み、1年で75%も農耕地が増えた。
そしてその機械化に呼応するように1986年以降、生産物の総販売価格が急激に上昇していく。一時はジョポイラ農協を死の淵へと追いやる手助けとなっていたドルレートとインフレがこの頃は追い風となって農協を助けた。
インフレの影響により農産物の価格は上昇し、大豆は1982年から1988年までに6倍に上昇、小麦は1984年から1988年の間に8倍にも上昇したのだ。そしてこの事実は生産拡大に拍車を掛けていくことになるのだ。
こうして1990年代におよそ16.000トンであった大豆の取扱量は2010年に43.703トンにまで大きくなり、パラグアイは大豆の生産で世界6位、輸出は4位の地位を得る事になったのだ。
大豆国際市場の値上がり背景
パラグアイの生産事情とジョポイラ農協の窮地についてみてきたが、イグアス農協にとって追い風となった世界的な大豆の市場の値上がりにも当然、理由がある。
ここではその背景を見ていこう。1970年台、大豆の国外輸出量はアメリカがダントツで一位だった。その当時アメリカは世界の大豆輸出のおよそ90%以上を生産し輸出していたが国内および国外での信用の失墜と作付面積の限界ならびに南アメリカの大豆輸出量の増加を背景にどんどんとそのシェアを失っていった。
時を同じくして、世界では食肉の消費量の増加や植物油の人気が高まるなどして、大豆需要が高まりを見せてきた。今回はそのアメリカの失墜と大豆の需要拡大に焦点をあてよう。
話は1960年台後半から始まる。当時、ヨーロッパ諸国をはじめ、日本や台湾などでは 畜産の振興 がすすめられていた。日本でもこの頃は米をあまり食べなくなり豚肉、鶏肉、牛肉を含め、バター、牛乳、チーズなどの乳製品もよく食されるようになった。
この当時日本の畜産農家に供給されている配合飼料の原料はアメリカから輸入される飼料穀物に依存していたがこれはその他、多くの国々も同じ状況であっただろう。
また当時、配合飼料と同様に世界中の畜産農家が栄養価の高い飼料として使っていたのがカタクチイワシ(アンチョビ)だった。しかし、1973年に食肉価格の急騰が始まる。当時エルニーニョ現象によって、カタクチイワシの漁獲高が激減し、市場に出回らなくなった。
その結果、アンチョビを重要な飼料としていた農家は食肉の価格を上げざるを得なかった。そして、これに代わる飼料原料として見つけたのが大豆だ。
これによって、世界中で大豆の需要が増大し1973年で前年比300%も値上がりした。また同年にインド、中国でも大豆や菜種などが不作となり、ますますアメリカの大豆需要は増していくこととなった。
この頃のアメリカは大豆を「シンデレラ・クロップ」「奇跡のマメ」とよび、この時代が大豆の「黄金時代」と呼ばれた。
加えて、人口増加も大豆需要に関わっていた。1970 年代の 10 年間に、世界の人口は 36.8 億人から 44 億人以上へ増えた。開発途上国の人口は 26.8 億人から 33.6 億人へ大幅に増えたが、先進国の人口も 10 億人から 10 億 8000 万人にまだ増え続けていたのである。
世界的に起こった食の高度化、食肉の消費拡大、そして人口増が進む中で、米国の農業界では誰もが大豆の黄金時代はさらに続くと信じていた。
穀物ブームに沸く一方、アメリカ国内ではニクソン大統領の再選を狙うグループが野党民主党の選挙対策本部に盗聴器を仕掛けようとして未遂に終わったウォーターゲート事件が発生。国民の不信感が頂点に達したときだった。
こうした中で、当時すでに世界最大の食肉生産国で、かつ最大の消費国でも あった米国では、飼料原料価格の高騰に苦しむ畜産団体と、食肉高騰に反発する消費者団体の両方がニクソン政権に対して事態の改善を求めていた。
ここでニクソン政権は威信の回復の為に大豆および大豆粕などの大豆製品と綿製品の輸出を前面に禁止すると突然発表し、これを断行した。日本でもこの時、大豆が原料となる豆腐、納豆、しょうゆ、味噌の値段が跳ね上がり、1973年当初1丁35円であった豆腐が70円以上に跳ね上がった。
この全世界を巻き込んだ割りに特別な信念や裏づけのない政策は同年10月1日には全面解除となったが。この騒動はアメリカ国民に対してだけでなくアメリカと関わる全世界の国々にとってもニクソン政権への不信感を強めるとともに、多くの食料輸入国が輸入先の多元化や食料自給の必要性を痛感した政策であった。
また、前述しているが1981 年には 1 億 9000 万 ha 近くに達したアメリカの大豆作付面積が限界を迎えることとなった。農地の一部が住宅地や道路、工場地帯へ転換される一方で、新た な耕地開発が不可能になったのだ。
それに呼応するように大豆の輸出額も 1982 年の 62 億ドルをピークに下落へ転じ、1990 年の 36億ドルの底に向けて減り続けることになったのだ。このようにして大豆輸出大国であったアメリカは国際競争力を失っていった。
しかし、世界の大豆需要は中国とEU諸国を中心に増加の一途をたどっており、白羽の矢が立ったのがほかならぬパラグアイを含めた南米だったのだ。当時はパラグアイの大豆生産量はほとんどなかったので中心はブラジルとアルゼンチンの大豆なのだが、いずれにしてもアメリカの独占市場だった大豆輸入・輸出はここから南米にシフトしていくことになったのだ。
不耕起栽培の成功理由(まとめ)
最後にパラグアイの大豆栽培が成功した要因の分析をしよう。前述の通り、不耕起栽培が取り入れられようとした時に、ジョポイラ農協(現:イグアス農協)ならびに組合員は大変な不遇の時代を乗り越えて来た。
ここではそのまとめとして、不耕起栽培の成功理由を挙げていこう。
1、国際協力事業団(JICA)パラグアイ事務所のソフトとハードに対する支援
2、大豆栽培に適した自然環境
3、イグアス移住地日系人の頑張りと勇気
4、大豆市場の拡大と幸運
5、除草剤とRR大豆
どんなにすばらしい技術であろうと農業はその土地にとって一番収穫が見込める作物を栽培しなければ上手くいかない。
まず、初めにパラグアイの肥沃な大地と降雨量、豊富な太陽量と自然環境が大豆栽培にとって適切であったことが成功の要因としかかせないだろう。
次に雨害による土壌流出とパラナ河を代表する生態系の維持を憂いて立ち上がったイグアス移住地日系人の存在だ。項目には頑張りと勇気という記載があるが、栽培方法を変更することにどのような勇気が必要なのだろうか。
ブラジルから不耕起栽培の情報が入ってきたとき「不耕起栽培導入から 3カ年は減収する」という懸念を専門家は話していた。それでも、不耕起栽培を行い土壌を守り、子孫へ自分の農場を継承する為に立ち上がったのだ。
また、当時ピラポ、ラパスを代表するイタプア県(パラグアイ南部)の地域では不耕起栽培について否定的な意見が多かった。
しかし、当時のイ グアス移住地は比較的新しい畑作地帯で慣行技術にとらわれず新しいものを受け入れる風土があった。そして地力も残っていたし、畑作の雑草も少なく環境的にも不耕起栽培 が成功しやすかったといわれている。
また、概要でも触れているがパラグアイ全国の日系農業者の技術支援をしていた海外移住事業団(後のJICA)が運営していたCETAPAR(セタパル)もその母体を1985年にイグアス移住地に移し、距離的にも最も新しい情報が得られたし、研究技術を吸収するのも容易であった。これはイグアス移住地へのJICAのソフト面での支援といえるだろう。
そして時を同じくして、イグアス移住地では、それまでトマトやメロンを主軸としていた営農が野菜の市場価格の低迷などにより伸び悩んでいたことに加え、栽培の難しさ(手作業が必要、雨が降ると収穫ができない。大規模栽培はできない)を背景に、野菜から不耕起栽培の導入を前提とした畑作への経営転換を図った時期でもあった。この頃、トラクター、コンバイン、播種機、消毒機などの設備支援を行った事はJICAのハード面の支援といえるだろう。
また、1986年から続く大豆の国際市場の値上がりと需要の高まりも大きな要因だった。アメリカが国際競争力を失い、世界が大豆を求め始じめた時期と不耕起栽培の導入時期が重なることは前述の通りだ。
最後に少し、不耕起栽培に欠かせなかった除草剤とRR大豆についてもみてみよう。不耕起栽培は品種選びと雑草との戦いだったといえる。はじめた当初は雑草に負けて耕起せざるを得ない状況になったり、朝顔などの雑草は除草に手間取ったそうだ。
その為、除草剤が欠かせなかったが当時は高価で、作付面積が増えれば増えるほど、生産コストも増大する悩みの種だった。それも除草剤は播種前、播種後、育成期、収穫前にと様々な種類の散布が必要だったのに加えてその効果も80%と頼りない数字だった。
1986年、1988年にはイマサキン剤とイマセタピル剤という2つの除草効果が認められる除草剤が登場し、農家は喜んだがこの2つの除草剤は化学成分が同じで5年以上続けて散布すると雑草が耐性を持ち始めてしまうというぬかよろこびに終わった。
少しときは流れて1992年。今日、世界でもっともよく使われているラウンドアップという除草剤に耐性を持つ遺伝子組み換え大豆(RR大豆)が開発されたと、アメリカのモンサント社が発表した。
通常の大豆はラウンドアップで枯れてしまうので播種前、もしくは発芽前の処理しか出来なかったがRR大豆は発芽後でも使用できるので雑草防除作業が楽になったという。しかし遺伝子組み換え大豆は農家は喜ぶが消費者はあまりいい顔をしないのは1990年代だけでなく現在でも同じだ。
現在のイグアス移住地では大部分の輸出用大豆のほとんどをRR大豆で作るなか、日本に向けて輸出するように遺伝子組み換えでない大豆も作っているとの事である。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。













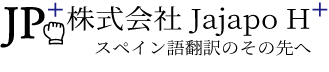
この記事へのコメントはありません。